「無駄が苦手で、怠惰を求めて勤勉になるタイプです」と語る、製造業のIT部門でプロジェクトマネージャーを担当されていた松本 恵和さん。RPAやビジネスチャットツールの導入によるDXや、予算3億円・2年半にわたるERP刷新など、数々のプロジェクトを推進されました。現在は合同会社つなぐ 代表としてDX事業、株式会社nico. 代表取締役として障害福祉事業を展開しています。今回は主に、DXでよく課題に挙がる経営層・現場との合意形成の取り方や、DXの推進で求められる人物像について、お話を伺いました。
年間7,800Hの業務時間を削減
――まず、松本さんが以前お勤めしていた会社の業種や、IT部門としてどのようなプロジェクトを推進されていたのか、お聞かせいただけますか?
勤めていたのは鋼鉄加工をしている会社で、自動車部品メーカー向けに材料を加工・販売していました。その会社のIT部門のプロジェクトマネージャーとして、ERPパッケージの導入・刷新はもちろんのこと、ERPパッケージだけではカバーしきれない部分を、VBAやPythonなどを用いてスクラッチ開発していました。
DXの観点では、経営層と現場側とリレーションを取りつつ、RPAやビジネスチャットツールなどを導入して効率化・コストカットし、社員のリソースを他の重要な業務に充てられるようにしました。
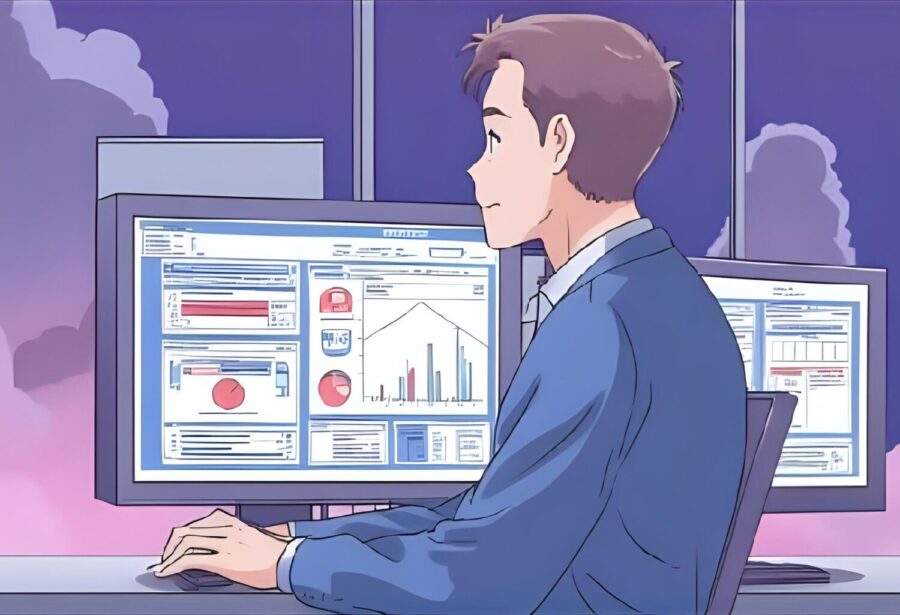
――さっそくですが、RPAの導入についてお伺いします。導入前の状態や、導入後の変化について、教えてください。
RPAの導入前には、現場で一番工数がかかっていた業務として、工場への作業指示がありました。一つひとつの作業指示を、人の手で一から入力するような業務フローになっていたのです。リピート性がある作業指示についても、人の手で一から作成していました。
そこで、リピート性のある作業指示については、以前の入力データをそのまま流用できるようにしました。ボタンを押すと過去の履歴を見れて、その内容を基に作業指示を作れるような仕組みです。リピート性が低い場合や、内容が難しい作業指示のみ、人の手で入力すればいいようにしました。
結果として、これまで10人程度の体制で年間9,000時間程度を費やしていた作業指示業務を、8割減の1,200時間程度に削減することができました。
――要件定義の工程ではどのような苦労がありましたか?
要件定義にはかなり力を入れて取り組みました。現場には業務手順書があったのですが、最新版に更新できていない状態になっていました。そこで、ITで業務改善できる範囲を洗い出すために、まずは現場にいるほとんどの社員から、業務内容をヒアリングして整理したんです。IT部門のメンバー3人だけで、半年くらいかけて対応しました。
ヒアリングしていくと、「業務手順書には載っていないけれど、やらないと業務が回らない」という独自のノウハウも存在しました。その部分も、システムに落とし込めるようにしていきました。

効率化はゴールに向かうために一手段
――DXを会社に提案するときに、経営層や社員に伝えてもなかなか合意形成できない、というパターンは多くの会社で起こり得ると思います。松本さんは、どのように周囲の人たちを巻き込んで、合意形成を取っていったのでしょうか?
プロジェクトをうまく動かすためには、経営層側と社員側のそれぞれに、異なる訴求を柔軟にすることが大切です。
まず、経営層に対しては、コストメリットの話をしていきます。「エンゲージメントが上がります」という訴求だけでもささる場合はありますが、売上を上げるよりも経費削減するほうが遥かに利益を上げやすいということもあり、最終的にはコストメリットの訴求が重要です。
ただし、エンゲージメントが上がるだけの施策だったとしても、「結果的に社員の生産効率が上がり、他の業務ができるようになるため、経費削減や売上UPにつながります」というストーリーはよく作っていましたね。経営層に価値を感じてもらって、現場に対してGOをかけてもらうことで、社員も柔軟に動いてくれて推進しやすくなります。
次に、現場にいる社員には、主に「業務が楽になる」という部分を訴求します。「導入したら効率化されて、業務が楽になります」と地道に時間をかけて説明していました。ただし、現場の社員全員から納得を得るのは難しいので、影響力の強いキーマンにしっかりと根回しして、味方につけてからプロジェクトをスタートさせることが大切です。
――業務側の方々が「導入したら仕事がなくなってしまうのではないか」と不安になって、プロジェクトがなかなか進まない現場もあるように思います。そのようなことはあまりなかったのでしょうか?
そうならないように、手を打っていました。まずはDXしていきたい管轄の部長に、例えば「部全体で、もっとやりたいことはないですか?」と聞くと、「本当はやりたいことがあるけれど、みんなの手が空いてなくて⋯」という回答を得ます。
そこで、「では、みんなが忙しいと感じている業務を今から効率化するので、◯時間が作れます。そうしたら、そのやりたいことはできますよね?」と伝えます。「そうだね」と同意を得られたら、今度は社員全員を集めて、今後の方向性をその部長から伝えてもらうようにしていました。
DXを進めるときには、効率化自体がゴールだと思ってしまいがちです。しかし、効率化はゴールではなくあくまで手段であり、効率化して時間ができたら、例えば営業体制を強化するなどの得たい何かがあるはずです。わたしがプロジェクトを推進したときにも、業務効率化の先のゴールをきっちりと社員には伝えるようにしていました。そのおかげで、社員からはそんなに否定的な意見は出なかったですね。
――先ほどのRPAの導入では、どのようなゴールを描いていたのでしょうか?
RPA導入のプロジェクトでは、そもそも現場にいる社員が毎日4時間くらい残業していたので、残業を減らすことが主な目的でしたね。「4→1時間に減らしましょう」と話をしていました。
ただ、その業務管轄のリーダーとしては、「利益を上げるキャッシュポイントを強化したい」という思いを持っていました。でも残業が多い状態で、社員には依頼できません。そこで、残業を減らしたらその話を出していこう、という裏目標もありました。

DX推進で求められるのは「コンサルテーションスキル」
――RPA以外にも、DXとして取り組んで大きな成功につながったことを、お伺いできますか。
コロナ禍になる以前からMicrosoft Teams(ビジネスチャットツール)を導入して、工場内のコミュニケーションの効率化を図りました。
Teamsを入れるときには、まだコロナ禍の前だったこともあり、周囲からは「なんでビジネスチャットなの?」と言われていました。しかし、当時の課題として、一部の社員だけが受電の一次対応をしていて、それから対象の人を工場内を探し回って呼ぶ、という大きな負担がかかっていました。
そこで検討した結果、従来の固定電話ではなく、Microsoftの電話システム「Microsoft Teams Phone」と市外局番を利用できるソフトバンクのシステム「UniTalk」を組み合わせて、社員それぞれの社用携帯電話に直通する電話番号を作ることに決めました。
そのプロジェクトを進めるにあたって、導入するメリットと、そのままの状態でいるデメリットを洗い出しました。まず導入するメリットとしては、「該当の社員に直通電話がかかるから、つなぐ手間が減る」が挙げられます。そのままでいるデメリットとしては、「既存の固定電話はとてもコストがかかっている」という状態がありました。
既存ではオンプレのPBX(交換機サーバー)を利用していたので、サーバーや交換機の利用費・保守費用がかかっていたのです。それらのコストと、Teamsの電話システムなどに置き換えたときのコストを比べたら、年間100万円近くのコストメリットがありました。
そして経営層に対して、コストメリットを見せるだけでなく、「入れ替えると社員のストレスが軽減して、エンゲージメントも上がります」と訴求し、「面白そうだからやってみよう」と返事をいただいたのです。
次に、現場にいる社員に対しては、「みなさんが電話に出ないから、一部の社員が困っています」とお伝えしました。電話ではなくチャットなどのいろんな機能が使えることや、電話する必要のないやり取りはチャットを使う運用にすることも同時に伝えて、プロジェクトを進めました。導入してからは3カ月ぐらいで定着し、現場のみなさんからは「楽になった」と言っていただきました。
その後にコロナ禍に入ったので、同業他社はコロナ禍の時期に「仕事が回らない」と困っている中、勤めていた会社では、事務所でパソコン作業している人をすぐにリモートワークに切り替えることもできました。

――次に、DXプロジェクトに関わる人材についてお聞きしたいです。松本さんは実際に、社員の採用から一人立ちできるまでを伴走された経験があると思います。社員またはベンダーを選ぶときには、どのようなスキルやマインドを持った人をアサインするとよいのでしょうか?
どんな職業でも言えることですが、まずは前向きであることがマストです。前向きでない人では、何も進まないからです。
スキルについては、しっかりと自分で調べる力がある人であれば問いません。実務の理解やコーディングなどができたらベターではありますが、後からでも身に付けられます。ただし、コミュニケーションの機会が多いので、コミュニケーション力は必須です。他にも、数字に強かったり提案時のストーリーを作れたりする人もいいですね。いわゆる、コンサルタントに求められるようなスキルかもしれません。
実際に、わたしの退職時に後任にした社員は、開発経験はまったくありませんでしたが、半年後には十分バリューを出していました。その社員は自分で調べる力やコミュニケーション力などの必要なスキルをすべて持っていたんですよ。生成AI(ChatGPT・Perplexity・Gemini)の使い方を教えてからは、AIを活用しながら開発できるようにもなりました。
AppSheet×GASで「現場目線」の自動化を実現
――現在は独立して、事業としてノーコードのAppSheet(Googleのノーコード開発環境)やローコードツールのGAS(Google Apps Script・ローコード開発環境)などを用いた業務自動化もされています。顧客からはどのような悩みが多く、その悩みに対して、どのようにコミュニケーションを図りながら価値提供されているのでしょうか?
ノーコード・ローコードツールを用いた業務自動化については、最近は林業・造園業・足場・建築など、共通して外に出て働く業種へのご支援が多いです。そこで主に求められているのが、見積書などの書類作成の効率化や、事故発生時の連絡手段の統一化です。
どの顧客も同じような悩みが多いので、汎用性のあるツールの作成を現在は進めています。軸となるツールを作成して、細かい部分は企業ごとにカスタマイズすれば、すぐに利用いただけるようになります。
――事故報告の共有は、ある程度AppSheetで作れそうだとイメージできました。見積書作成については入力やテンプレートを整えることが必要と思いますが、具体的には何をどのような開発環境を使って作成しているのでしょうか?
事故報告の共有ツールと見積書作成ツールの両方ともAppSheetで作成し、同じアプリ内で使えるようになっています。顧客にデモを見せた際には、「すごくいいですね」と言っていただけました。
ただし、AppSheetだけだと見積書PDFを払い出したときのテンプレートの見た目があまりよくないので、Excelで作成したテンプレートを使えるように、GASで構築しようと考えています。基本情報をAppSheetから出して、その情報を基にGASでPDFにしてメールで送る、というような仕組みですね。

DXは「運用改善」ではなく「わかりやすい効果」から始まる
――DX推進する上で、一番ネックになるポイントと、その解決策を教えてください。
自分の強みでもあると思いますが、実務をわかっている人のほうが、本当に使いやすいものを作れると思っています。例えば、画面構成の一部を変えるだけで、すごく使いやすくなる場合があります。しかし、機能要件だけしかわかっていないと、「機能さえ満たしてしまえば十分」と考えてしまいがちです。
わたしの場合は長く製造業に携わっていたので、使いやすい画面遷移や、現場でITに詳しくない人でも使いやすくする工夫など、DXを進めるときにネックになるポイントを最初から押さえて設計から導入まで進められます。
また、電子契約など、「本当はこれを使ったら楽になるな」と思うツールはたくさんあります。しかし、IT知識が少ない顧客の場合は「よくわからない」という状態になってしまうんですよ。その状態で、「運用を変えてください」と言うのは少し違うと思っていて、実は現場はそこまで困っていない場合もあり、現時点では優先度が低いんですよね。
そこで、まずは一番困っているポイントを聞いて、わかりやすい効果を感じていただくことを重視しています。そうすると、後から他にも困っているポイントが出てきますし、その後の提案もしやすくなります。
――「いろんなツールを使って業務効率化しましょう」と提案するのではなく、まずは現場で一番困っていることに対して、効果がわかりやすいものを提示していくということですね。そのほうが顧客側は喜ぶし、ビジネスとしても成立しやすい。
最近は、よいサービスを作る「プロダクトアウト」だけではなく、市場で需要のあるサービスを作る「マーケットイン」という考え方を大切にしています。
ただよいと思うサービスを作ったところで、求められていなかったら売れません。求められたものを提供していくほうが、顧客から価値を感じてもらいやすいです。「プロダクトアウト」として顧客がサービスを導入すれば効率化できるのはわかっていますが、提案のミスマッチが起こる可能性があるので、あえて言わないようにしています。
――最後に、松本さんの今後の展望を教えてください。
わたしは人から「ありがとう」と言われるのが一番好きなので、そこを軸として今後も事業展開していく予定です。障害福祉事業については、多店舗展開しつつ、その福祉の現場でDXを推進していきたいと考えています。現在、運営している福祉施設は1つのみですが、5年以内には5施設にしていく予定です。同時に、DX事業の売上も増やしていきたいです。

合同会社つなぐ HP<開設中>
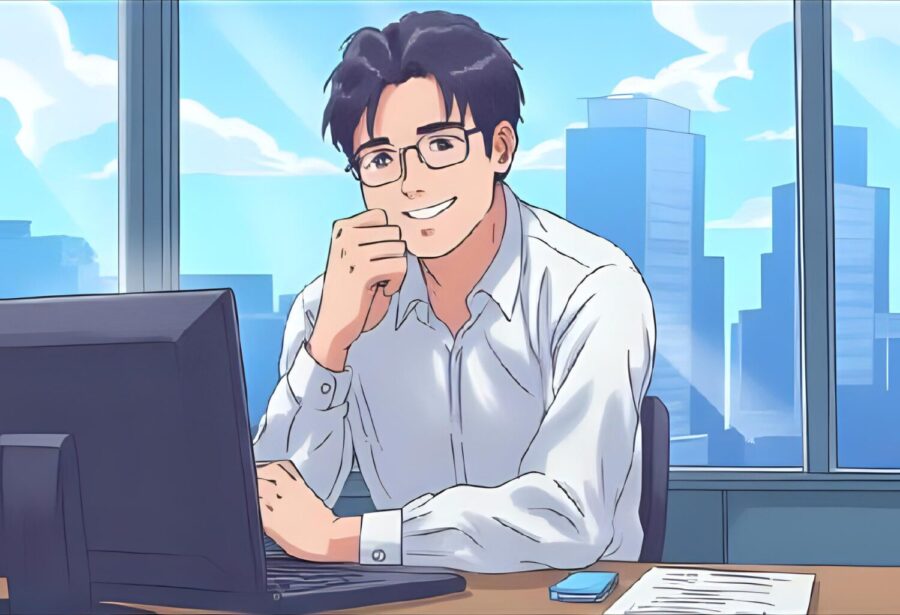
コメント