日本企業全体で、2025年卒の大卒求人倍率は1.75倍と、3年連続で上昇傾向。従業員300人未満の企業では、6.5倍に跳ね上がっている。そして、正社員が不足している企業は53.4%にのぼり、新卒採用を予定している中小企業全体の30.8%にとどまるなど、採用難はますます深刻化している。
そんな逆風下で半導体商社の採用責任者を務めた江口武志氏は、あえて「真面目じゃない理系学生」をペルソナに設定。1対3の超少人数説明会と面接前後のフォローを徹底し、母集団の減少を最小限に抑えながら毎期の採用目標を達成してきた。本インタビューでは、中小企業が新卒採用を成功させるために必要な考え方や、具体的な採用プロセスを伺った。
「真面目ではない新卒」がペルソナ
松戸|中小企業が実践すべき採用手法や考え方について、いろいろとお聞きできればと思います。まずは、江口さんのご経歴を教えていただけますか。
江口|前職では100名規模の半導体商社で、BtoBの営業と営業サポートを10年、新卒採用を10年担当していました。半導体は作るまでに3〜4カ月かかるので、顧客が必要としているときに、タイミングが合わずにすぐに渡せない場合があります。営業をしていた当時のわたしは、顧客に対して過不足なく半導体を共有できるように、顧客と一緒になって需要の管理をしたり、在庫管理したりすることが得意でした。

顧客と一緒に管理する能力を当時の会社からは目をつけていただき、商品管理を主とした営業サポートの役回りになりました。営業サポートを5年経験したのち、営業の現場を熟知していたことから管理部に異動して、営業職の新卒採用に携わるようになりました。
松戸|半導体商社の新卒採用の場合、どのようなペルソナを作るのでしょうか。
江口|ペルソナ像を作るのは、とても苦労しました。半導体の営業は、理系の小難しい知識と、コミュニケーション力の両方が求められます。ただし、半導体の基礎的な知識は入社してから身につければいいので、どちらかというとコミュニケーション力を重視。かつ、「理系の知識はあるけれど、真面目に勉強してない学生」をターゲットにしていました(笑)
松戸|面白い着眼点ですね。一般的には「真面目ではない人」には焦点を当てないと思います。なぜ焦点を当てることにしたのでしょうか。
江口|「不真面目」は悪い意味に捉えがちですが、裏を返すと「いろんな経験をしてる」と捉え直しました。営業職は少なからず、自分自身の経験をもとにして、顧客とのコミュニケーションを育むという側面があると思います。そこで、勉強一筋ではなく、たとえば多くのバイトを経験したり、友達とたくさん遊んだりしている人の良い面を見るようにしました。「真面目ではないが経験豊富な学生」というペルソナに合致した学生が入社した結果、実際に活躍しているケースは多いです。
松戸|「不真面目な人」はアイディアが豊富で、入社後もいろんなことを試すような素質があるように思います。
江口|まさにそのとおりです。入社してはじめの頃は、さまざまな試みをして先輩から怒られる場面もよくありますが、伸びしろはすごくあります。
面接前後で候補者の「素」を把握する
松戸|ペルソナに合う人以外にも、良いと思った人は採用されていたのでしょうか。

江口|ペルソナから外れていても、「いいな」と思う人は確かにいました。しかし、そのような人は、入社してからの活躍が目に浮かびません。たとえば、すごく地頭が良い候補者がいたのですが、採用部内で話した結果、「喜んで働いている絵が浮かばないよね」ということがありました。頭の回転は早いけれど、入社した後に苦労するか辞めてしまうリスクが高い。よってペルソナ像にしっかり収まる人を見つけることを、とても意識していました。
松戸|ペルソナ像をつくるとき、つい「スキル」や「学歴」などの条件面に偏りがちですが、「価値観が合うこと」は一層重要であるように思います。とはいえ、価値観というのは定義が難しく、社内でもなかなか言語化できない。この点についてどのように整理されましたか。
江口|そうですね、ついラベルを貼りたがる傾向があると思います。自社でも、上層部から「地頭がよい人がいい」という意見があったのですが、採用側ではその基準を外したことがありました。地頭が良くてもコミュニケーションができなければ、商社の営業としては活躍できない、という理由からです。
候補者への会社説明会では、コミュニケーションが活発であることや、社員同士の仲が良いことなど、「価値観」の部分をなるべく伝えるようにしていました。そうすると、学生たちも「自分もそういう雰囲気に合っていると思います」と話してくれることが増えて、そこに対して「どのあたりが合っていると思うの?」と質問するなど、深掘りもできるようになりました。
松戸|価値観や人物面は、履歴書や職務経歴書からは読み取りづらいと思います。候補者の価値観を理解するために、良い方法があれば教えてください。
江口|会社説明会をした後は、一次、二次と対面の面接が続きますが、一次面接の直前と直後には必ず、採用部のメンバーが候補者に立ち会う時間をつくるようにしていました。そのときの約束事として、「我々は企業側ではなく、あなたの100%の味方だから、この場はリラックスしていいよ」と伝えます。心境などを聞きつつ、面接対策のアドバイスもするんですよ。
たとえば、「今日の面接官は第一営業部のAさんと第二営業部のB課長。B課長は少し厳しいから、気にしすぎなくて大丈夫。困ったときはAさんを見れば、笑っているから安心できるよ。」というように。そうすると、緊張度や他社の選考状況なども把握しつつ、書類や面接だけでは見えない候補者の素の姿が見えるようになります。

面接が終わった後は、候補者に付き添った採用メンバーが会場に入って、面接前後の様子をあくまで一つの情報として面接官にフィードバックします。そうすると、面接時と面接前後の人となりが合致しない場合があります。ギャップが大きい場合は、本音を出しきれていないという面もあると思いますが、採用は見送ります。反対に、面接前後と面接中でギャップが少ない人は、自分のやりたいことの落とし込みができていると判断します。
それ以外にも、良いなと思った学生には、一次面接と二次面接の間の日程で、先輩社員と会話する機会を30分の1on1で設けました。そうすると、学生の本音をさらに引き出すことができます。このような取り組みをした結果、面接の場で「面接前に話した人がいたから、入社したいと思いました」と面接の場で言ってくれる学生もいました。
採用された側も感動する採用手法
松戸|採用で、一番印象に残ってるエピソードや成功例を教えてください。
江口|面接前後のケアをした結果、入社したい思いが強すぎて、二次面接のときに泣いてしまった学生がいました。それぐらい「入社したい」と思ってもらえたことがうれしくて、未だに印象に残っています。どうせだったら採用活動を通して学生に喜んでもらえるようにしたい、と考えていたので、一つの理想を形にできたと思います。
残念ながら見送りにした人からも、「見送りになった理由を教えてほしい」と電話がかかってきたり、「どうしたらもう一度面接できますか」と聞かれたりしました。そのときは「もう一度の面接は難しい」と伝えたうえで、見送りにした理由を丁寧に伝えました。
中小企業で人数が少ない会社だったので、求職者からは「人」をよく見られると考えて、なるべく人臭さを出すことを意識していましたね。
松戸|一方通行の採用ではなく、「採用された側も感動する採用手法」にもこだわっていらっしゃます。そのあたりもお伺いしていいですか。
江口|はい。採用担当として、ミスマッチは嫌だなと思っていました。採用の世界では、「いい人を採用したいがために自社をよく見せる」というのは、良くあることなんです。しかし当然、リップサービスを真に受けて入社してしまったり、イメージしていた会社の雰囲気が違ったりして、離職につながってしまいます。誇張したり想いを伝えすぎるのではなく、「自社に合う人」を探すことをすごく意識しました。
松戸|なるほど。それで先ほどの「真面目ではない新卒」というペルソナ像につながるのですね。

江口|決して効率的ではないのですが、ひたすらに学生と話すような採用手法で、1人の学生に多くの時間を使いました。他の会社にはないような、一見なんの会場かわからないような、柔らかい雰囲気の会場になるようにも努めました。
松戸|学生の素が出るような。
江口|そうです。すごく面白かったんですよ。実験としてやったのが、お茶やコーラなど、多種多様の飲み物を会社説明会の会場内に用意。多くの学生はお茶を選ぶのですが、その中でコーラを取る学生に注目して説明会中の行動を追いかけるなど、あまり採用という硬い雰囲気にならないように意識しながらやっていましたね。
松戸|良くある採用の硬い雰囲気ではなく、人の素が見れるような雰囲気作りはとても大切だと思いました。自社に合う人を見つけるために、1人の候補者に対しては、どこまで深掘りするのでしょうか。
江口|採用についての会話だけにとどまらず、可能な限り詳しく話を聞いて、1人の学生が「何をやりたいのか」まで入り込んで話をします。たとえば、営業職向きではない学生には、「苦労してしまうから、営業ではない職種の方が向いているかもしれない」と話したり、「当社のような商社ではなく、メーカーの営業の方が向いているかもしれない」と伝えたりなど、目の前の学生のことを考えて、本当にざっくばらんに話をしていました。
松戸|採用活動だけではなく、「人」に寄り添っていて、表現が合っているかわかりませんが、根本に「愛情」があるように感じました。
江口|これまでやってきた採用方法は、その「愛情」という言葉が一番しっくりきます。どうしても採用というと、指定の人数を採用するというミッションに重さを感じて、行動自体もそこに比重をかけがちですが、私は運がいいことに「自社に合う人の採用」にチャレンジできました。
中小企業の採用は「機動力」が鍵
松戸|「自社に合う人の採用」という質の部分だけではなく、目標採用数も毎期100%達成されていました。「質」を担保しつつ「量」も達成するために、工夫したポイントを教えてください。
江口|中小企業なので、「大手企業と同じ採用手法では勝てない」と考えて、同じことは絶対しないと決めていました。大企業と同じように、数百・数千人単位の会社説明会から最初の母集団を作るのは、パワーが必要なそもそも無理な手法で、質も荒くなりがちです。
一度、会社説明会に無理矢理50人集めたことがありましたが、採用を進めていく中で、面接に至ったのはたったの数人でした。これでは、10人集めたときと変わりがなく、労力がかかっただけで意味がありません。この反省から、まずは母集団が減っていく原因を分析しました。

大人数を集めた場合の会社説明会は、大企業に目が向いていたり、自社のことが好きではなかったりする人も来てくれるぶん、荒い母集団になってしまいます。そこで、最初の入口である会社説明会の精度を高めることにしました。やり方としては、大人数の会社説明会は完全にやめて、採用メンバー1人対学生3人程度の小規模の場を多くつくり、機動力で勝負。
少人数の会社説明会にすることで、価値観を擦り合わせつつ、学生との距離もぐっと縮まります。結果的に、会社説明会に参加した学生の8割程度を面接につなげることができて、会社説明会から面接の動線が、圧倒的に改善しました。
少人数の会社説明会では、お会いした時点から、学生3人とも顔と名前が一致している状態です。また、一方的に定型の説明をするというよりは、「〇〇さん、どうですか?」という具合に、じっくり対話することを心がけました。説明会が終わったときには、ある程度仲良くなっている状態になるように、説明会という採用のスタート地点をとても大切にしました。
松戸|少人数の会社説明会では、学生と会話する採用メンバー側のコミュニケーション力が重要になりそうですね。目標である毎期2〜3名の採用を達成するために、半期で何回くらい少人数の会社説明会を開催したのですか。
江口|多いときには半期で100回くらい開催しました。学生たちが動き出す2月くらいから、説明会をたくさん設けます。大手企業への入社を逃した学生へのアプローチを狙っていたので、特に4月からが本番と考えていました。4月〜6月の期間は毎日のように開催し、午前と午後で2回開催する日もありました。
経団連に加盟しているような、一部の大手企業では、新卒募集の解禁日が毎年3月1日に定められています。大手求人サイトの担当者からは、「他社と同時期の3月に本腰を入れないと、負けてしまいますよ」と言われましたが、同タイミングでは大手企業の冠に勝てないと考えて、あえてそのアドバイスはスルーしてましたね(笑)私が学生の立場に立っても、大手企業と中小企業があったら、大手企業を最初に選んでしまうと思ったからです。
「いい会社」に入るより「やりたい仕事に就く」ことが大切
松戸|大手企業に合わない人は、少なからずいますよね。断定はできないと思いますが、大手企業には合わない人には、江口さんから見てどのような特徴があるとお考えですか。

江口|すぐにいろいろとチャレンジしたい人などは、どんなに優秀であっても、あまり大手企業には合っていない傾向があると思います。企業によりますが、大手企業はルールが固まっているために、なんでもすぐにチャレンジできるわけではないからです。
しかし、大手企業未満、ベンチャー企業以上の規模感の中小企業には、いろいろとチャレンジしたい人物はマッチすると思います。中小企業はある程度の土壌が整っているけれども、人が少ない分、早い段階で仕事が任されるようになります。
たとえば、大手企業では5年かかるところを、中小企業では3年で次の経験ができる可能性があります。ベンチャー企業については、入社して成果を出せればすごいことですが、求められることは多くてハードルが高く、働く環境も厳しい場合があります。このようなミスマッチを起こしている学生は結構いるので、その人たちにアプローチするイメージですね。
松戸|今後、個人事業主として事業にチャレンジしていくと思います。どのような事業をお考えでしょうか。
江口|二つ考えています。一つ目は、上手に採用活動できていない中小企業へ、採用コンサルタントとしてアドバイスすることです。
二つ目は、キャリアコンサルタント資格も活かし、長年の採用経験がある立場から、学生に取って本当に良い進路をアドバイスすることです。採用の仕事で多くの学生とやり取りする中で、やりたいことではなく、いい会社に入ろうとしている学生が多いことに気付きました。「やりたいこと」と「いい会社に入ること」には違いがあり、結果的に離職につながる場合が多いです。
世の中には、たしかにいい会社はたくさんあります。しかし、「いい会社」に入るためではなく、「やりたい仕事に就く」ためのキャリアアドバイザーになれたらと考えています。
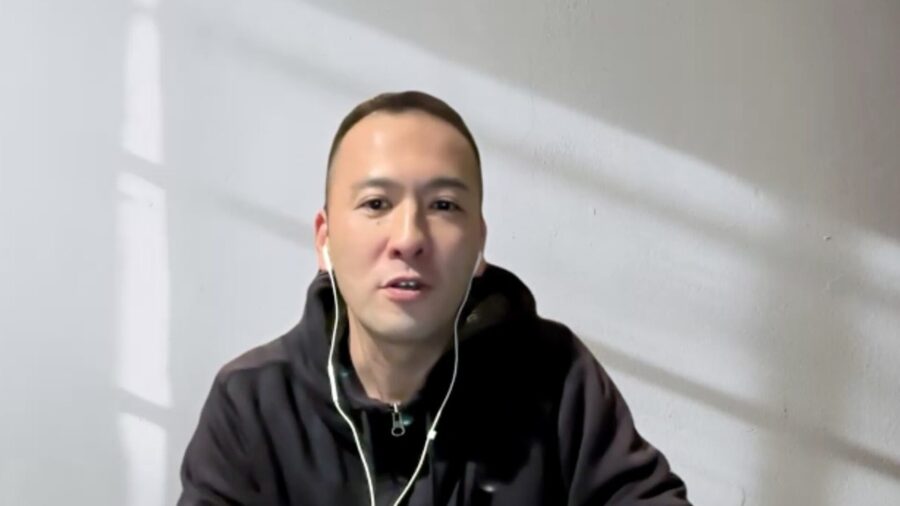
江口武志氏のSNS

コメント